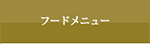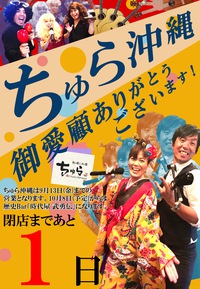2015年04月06日
日本酒買いに、新潟へ #.2
〜前回のあらすじ〜
色々な偶然と縁が偶然が重なり、日本一の銘酒「鶴齢」の
香港・沖縄での代理店になるべく、私と弊社代表真由美ボスは
飛行機と新幹線と電車を乗り継いて、3月末にして
2mの積雪を超える豪雪地帯、新潟県は南魚沼市、塩沢の駅へと降り立った。
そこに待ち受けていたのは、積雪対策で道路が凍結しないように
中央分離帯から自動でお湯が出る装置。
始めて目にする豪雪地帯の生活の知恵にテンションの
感動した真由美ボスは、道路のド真ん中で
写真を撮りまくるのであった。
(前回の詳しい記事はコチラ↓↓)
http://enokinawa7588.ti-da.net/e7437671.html
辿り着いた塩沢駅前の青木酒造。
「こんにちは〜」とドアをくぐり抜けると如何にも人の良さそうな
おじさんとおねぇさんが我々を迎え入れてくれた。
「香港から来たEN Groupです」
「あぁ、ゴメンねぇ〜、コッチじゃなくても
うちょっと先の事務所の方に行ってもらってもいいかね〜?」
どうやら、行く場所を間違えたようです。
「良かったら乗って行きますか?」
と声を掛けて下さったので、お言葉に甘えて
少し先の事務所までおじさんお運転するトラックに
乗せて頂くことにした。
そして辿り着いた、青木酒造の出荷場兼事務所。

広い敷地に大きなトラックやフォークリフトが点在しており、
新潟の中では小規模とはいえども、流石は日本一の
酒どころともいうべき風格があります。

中で出迎えて下さったのは、取締役統括部長の阿部さん。
シンガポールはじめ、アメリカなど海外での営業実績もある
青木酒造の顔役共いうべき方です。
小一時間ほど有意義なご商談をさせて頂きました。
(私はほとんど横でお話を伺っているだけでしたが)
さてここで、青木酒造様について少しご紹介します。
創業は何と、今から298年前の1717年!!
「暴れん坊将軍」で有名な第8大征夷大将軍徳川吉宗の時代、
享保2年で再来年には創業300周年を迎える、新潟県最古の酒蔵です。
先ほどから名前が出ている「鶴齢」シリーズを筆頭に、
「雪男」、「鶴齢梅酒」、そして最上級グレードの「牧之」など、
歴史とともに進化した、幅広いラインナップを有しています。
味については後述します。
詳しい情報には、青木酒造Webページをご覧下さいませ。
→http://www.kakurei.co.jp/index.php
さてm一通りのお話しをお伺いしたのち、
ご無理を言って銘酒「鶴齢」の生産される工場の中を
見学させて頂けることになりました!!

↑販売所兼工場の前で、真由美さんと阿部さん
江戸時代風の町並みがきれいに整備された塩沢の
メインストリートの一角に青木酒造の工場兼販売場はあります。
販売所の軒先にはいい色に枯れた「杉玉」が。

その名の通り、杉の葉を集めて作るボール状のオブジェで、
別称「酒林(さかばやし)」。「日本酒を搾りはじめました」
という意味で軒先に吊るし、最初は緑色をしているのですが、
日数が経つごとに茶色に変色し、その枯れ具合が
新酒の熟成具合を物語るといわれています。
販売所のとなりの細い路地を抜けると、
建物の裏手、ちょうど家と家の間に、表からは全く想像できな程
大きなタンクに囲まれた酒造所が姿を現しました。
入り口で白衣と長靴に着替え、きっちり消毒をしてから中へ。
入り口には原材料になるお米の入った袋が
整然と積み上げられていました。

日本酒用の米は、地元新潟の「五百万石」はじめ、
「山田錦」、「こしいぶき」、「美山錦」など、
酒により様々なお米を使い分けるとのこと。
使用する水は、地下80mから組み上げる
豊富な雪解け水を水源にした地下水。

ちなみに、南魚沼市は米どころであると同時に、
水が大変美味しいことでも知られています。
上質な軟水は酒造りにはもちろん、
お米を炊いてもふっくら艶やか。
日本茶を入れても最高です。
2階に上がると、密閉された部屋の中で、
男たちが、大きなちり取りのようなもので、
目の前にうず高く積まれた白い塊にバッサバッサと風を送ったり、
手でかき回したりして何やら忙しく動き回っています。

以下に室内とはいえども、我々がいる建物の中は
推定気温は一桁。コートを着ていても肌寒いくらいなのに、
何故か中の男たちは上半身裸なのです。
「麹室(こうじむろ)で麹米を作っていることろです」
とのこと。簡単に説明すると、日本酒を作る上で欠かせないのが麹米で、
蒸した米を「麹室」とよばれる部屋で麹と混ぜ合わせ米麹を作っていきます。
麹を繁殖させるために、室内の気温は常に40度以上という極限状態。
この温度じゃないと麹菌がうまく繁殖しないそうです。
機械を使わず全てが手作業。麹菌は酵素が強いので、
混ぜ合わせる作業をしていると素手だと手が荒れるそうで、
4名いる作業員は基本的に手袋をしているのですが、
その中で一人だけは素手のまま作業をしています。
何故かというと、何と!!温度計でも測ることが出来ない微妙な
温度の誤差を素手で測って常に最高にして一定の品質の
麹米を作り出しているとのことなのです!!
恐るべし、匠の技!!
ちなみに、この技を体得するためには
7年もの歳月を要するとのこと。
うーん、お見それしやした。
そうした職人技の粋を結集し、
さらに丸2日を掛けて出来上がった麹米がコチラ。

日本庭園の玉砂利のように美しい起伏と
模様を描かれた麹米は、ひっそりと酒として醸造されるのを
待っているかのようでした。
つづく。
えん沖縄 Tel 098-941-7588
E-mail en@en-okinawa.com
EN Garden Tel 098-869-3058
E-mail en-garden@en-okinawa.com
お陰様で録者数ついに5000人突破!!お友達追加で得すること間違いなしな、
えん沖縄のLINE公式ページ。皆様登録宜しくお願いします!!

お陰様でお友達登録者数4000人突破!!
EN GardenのLINE公式ページ、皆様お友達登録お願いします!!

一番タイムリーで旬な情報満載!!
えん沖縄のFacebookページはコチラ!!
↓ ↓ ↓
http://en-okinawa.com/
↓↓↓メニュー全種類見れます!!えん沖縄ウェブサイトはコチラ
http://en-okinawa.com/
色々な偶然と縁が偶然が重なり、日本一の銘酒「鶴齢」の
香港・沖縄での代理店になるべく、私と弊社代表真由美ボスは
飛行機と新幹線と電車を乗り継いて、3月末にして
2mの積雪を超える豪雪地帯、新潟県は南魚沼市、塩沢の駅へと降り立った。
そこに待ち受けていたのは、積雪対策で道路が凍結しないように
中央分離帯から自動でお湯が出る装置。
始めて目にする豪雪地帯の生活の知恵にテンションの
感動した真由美ボスは、道路のド真ん中で
写真を撮りまくるのであった。
(前回の詳しい記事はコチラ↓↓)
http://enokinawa7588.ti-da.net/e7437671.html
辿り着いた塩沢駅前の青木酒造。
「こんにちは〜」とドアをくぐり抜けると如何にも人の良さそうな
おじさんとおねぇさんが我々を迎え入れてくれた。
「香港から来たEN Groupです」
「あぁ、ゴメンねぇ〜、コッチじゃなくても
うちょっと先の事務所の方に行ってもらってもいいかね〜?」
どうやら、行く場所を間違えたようです。
「良かったら乗って行きますか?」
と声を掛けて下さったので、お言葉に甘えて
少し先の事務所までおじさんお運転するトラックに
乗せて頂くことにした。
そして辿り着いた、青木酒造の出荷場兼事務所。
広い敷地に大きなトラックやフォークリフトが点在しており、
新潟の中では小規模とはいえども、流石は日本一の
酒どころともいうべき風格があります。
中で出迎えて下さったのは、取締役統括部長の阿部さん。
シンガポールはじめ、アメリカなど海外での営業実績もある
青木酒造の顔役共いうべき方です。
小一時間ほど有意義なご商談をさせて頂きました。
(私はほとんど横でお話を伺っているだけでしたが)
さてここで、青木酒造様について少しご紹介します。
創業は何と、今から298年前の1717年!!
「暴れん坊将軍」で有名な第8大征夷大将軍徳川吉宗の時代、
享保2年で再来年には創業300周年を迎える、新潟県最古の酒蔵です。
先ほどから名前が出ている「鶴齢」シリーズを筆頭に、
「雪男」、「鶴齢梅酒」、そして最上級グレードの「牧之」など、
歴史とともに進化した、幅広いラインナップを有しています。
味については後述します。
詳しい情報には、青木酒造Webページをご覧下さいませ。
→http://www.kakurei.co.jp/index.php
さてm一通りのお話しをお伺いしたのち、
ご無理を言って銘酒「鶴齢」の生産される工場の中を
見学させて頂けることになりました!!
↑販売所兼工場の前で、真由美さんと阿部さん
江戸時代風の町並みがきれいに整備された塩沢の
メインストリートの一角に青木酒造の工場兼販売場はあります。
販売所の軒先にはいい色に枯れた「杉玉」が。
その名の通り、杉の葉を集めて作るボール状のオブジェで、
別称「酒林(さかばやし)」。「日本酒を搾りはじめました」
という意味で軒先に吊るし、最初は緑色をしているのですが、
日数が経つごとに茶色に変色し、その枯れ具合が
新酒の熟成具合を物語るといわれています。
販売所のとなりの細い路地を抜けると、
建物の裏手、ちょうど家と家の間に、表からは全く想像できな程
大きなタンクに囲まれた酒造所が姿を現しました。
入り口で白衣と長靴に着替え、きっちり消毒をしてから中へ。
入り口には原材料になるお米の入った袋が
整然と積み上げられていました。

日本酒用の米は、地元新潟の「五百万石」はじめ、
「山田錦」、「こしいぶき」、「美山錦」など、
酒により様々なお米を使い分けるとのこと。
使用する水は、地下80mから組み上げる
豊富な雪解け水を水源にした地下水。
ちなみに、南魚沼市は米どころであると同時に、
水が大変美味しいことでも知られています。
上質な軟水は酒造りにはもちろん、
お米を炊いてもふっくら艶やか。
日本茶を入れても最高です。
2階に上がると、密閉された部屋の中で、
男たちが、大きなちり取りのようなもので、
目の前にうず高く積まれた白い塊にバッサバッサと風を送ったり、
手でかき回したりして何やら忙しく動き回っています。
以下に室内とはいえども、我々がいる建物の中は
推定気温は一桁。コートを着ていても肌寒いくらいなのに、
何故か中の男たちは上半身裸なのです。
「麹室(こうじむろ)で麹米を作っていることろです」
とのこと。簡単に説明すると、日本酒を作る上で欠かせないのが麹米で、
蒸した米を「麹室」とよばれる部屋で麹と混ぜ合わせ米麹を作っていきます。
麹を繁殖させるために、室内の気温は常に40度以上という極限状態。
この温度じゃないと麹菌がうまく繁殖しないそうです。
機械を使わず全てが手作業。麹菌は酵素が強いので、
混ぜ合わせる作業をしていると素手だと手が荒れるそうで、
4名いる作業員は基本的に手袋をしているのですが、
その中で一人だけは素手のまま作業をしています。
何故かというと、何と!!温度計でも測ることが出来ない微妙な
温度の誤差を素手で測って常に最高にして一定の品質の
麹米を作り出しているとのことなのです!!
恐るべし、匠の技!!
ちなみに、この技を体得するためには
7年もの歳月を要するとのこと。
うーん、お見それしやした。
そうした職人技の粋を結集し、
さらに丸2日を掛けて出来上がった麹米がコチラ。

日本庭園の玉砂利のように美しい起伏と
模様を描かれた麹米は、ひっそりと酒として醸造されるのを
待っているかのようでした。
つづく。
えん沖縄 Tel 098-941-7588
E-mail en@en-okinawa.com
EN Garden Tel 098-869-3058
E-mail en-garden@en-okinawa.com
お陰様で録者数ついに5000人突破!!お友達追加で得すること間違いなしな、
えん沖縄のLINE公式ページ。皆様登録宜しくお願いします!!
お陰様でお友達登録者数4000人突破!!
EN GardenのLINE公式ページ、皆様お友達登録お願いします!!
一番タイムリーで旬な情報満載!!
えん沖縄のFacebookページはコチラ!!
↓ ↓ ↓
http://en-okinawa.com/
↓↓↓メニュー全種類見れます!!えん沖縄ウェブサイトはコチラ
http://en-okinawa.com/
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。